9月20日(月曜日)敬老の日でもあり彼岸の入りにお墓参りに行き来ました。
お墓参りは、毎年彼岸の入りに行くのが恒例になっています。
昨日は晴天に恵まれたシルバーウィーク最終日。
現在では、お墓参りが当たり前であった過去とは異なり、後継者が高齢化し、跡継ぎがいない問題が深刻化しており、真剣に考える必要がある時代になりました。
お墓参りと承継(相続)

お墓参りに行くと足元おぼつかない高齢のお年寄りがお付きの人と一緒に来られているのを目にします。
お墓参りを若い家族に任せることなく自らお参りをする。
高齢者にとってはご先祖さまを供養することは当たり前であって、精神的な拠りどころであるようです。
私の父は難病で歩くこともままならないのに、亡くなる年のお彼岸に「這ってでも行く!」と言って、酸素ボンベを引きながらお墓参りに同行したことがあります。この思い出は今でも私の心に深く刻まれています。
私は子どもの頃から、家庭にある仏壇に手を合わせ、毎年のお墓参りにも同行することが当たり前でした。しかし、現代では核家族化が進み、仏壇のない家庭が増えているため、先祖の供養についての認識が薄い人も多いのではないでしょうか。そのため、お墓の承継(相続)問題について理解が不十分な人が増えています。
お墓の承継(相続)とは

先祖の供養が日常にない暮らしをしている世代が増える中、お墓の承継(相続)問題が深刻化しています。お墓の名義人(使用権を取得している人)が亡くなった場合、お墓や仏壇をどうするか事前に準備をしておくことが必要です。
お墓の承継(相続)とはお墓の名義人(使用権を取得している人)が亡くなった場合、そのお墓は「祭祀財産(さいしざいさん)」となるため、これを相続する「祭祀承継者」を決めることです。 そして、祭祀財産は分けられないので一人で承継(相続)することになります。
※祭祀財産(さいしざいさん)とは、家系図、仏壇(仏像や位牌など)、墓碑、墓地などです。
祭祀財産を承継しても、お墓の管理ができない場合は、祭祀財産を処分することも可能です。つまり、お墓の管理ができなくなった場合、祭祀財産の意義もなくなってしまうため、そのまま放置するよりも処分することが望ましいとされています。
※墓じまいとは、お墓からご遺骨を取り出し、墓石を解体・撤去し墓地を更地にして使用権を墓地の管理者に返還することです。
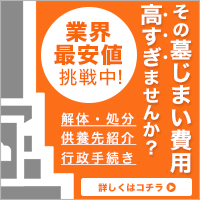
昔から先祖代々引き継がれたお墓は家長が亡くなると、配偶者やその家の長男が引き継ぐことが一般的でした。しかし、現在の日本では少子化や核家族化が進み、お墓の承継(相続)が課題となっています。
樹木葬や永代供養、海洋散骨など様々な納骨方法が増えたことで、お墓を必要としないと考える人も増えています。

お墓に対する若い世代の意識

お墓に対する若い世代の意識調査によると、意外にも60%以上の人がお墓が必要だと考えていることがわかりました。
■お墓が必要とする人の理由:
先祖と自分「家族の繋がりを感じられるから」
■お墓は不必要とする人の理由:
「必要性を感じない」や「管理の手間がかかるから」
「お墓は必要」と考える場合、お墓の承継(相続)にはお墓の管理に加え、お寺に対する費用も意識しておく必要があります。檀家であれば入檀や離檀、お布施の他に、お寺の大規模な改修工事による寄付なども必要になる場合があります。
うさぎやさんとお月見

お墓参りの後のお楽しみはぶらぶら散歩。
美術館や動物園にも寄りたいけれど、コロナ禍だからあまり動き回らず家族の好きなうさぎやさんの看板商品のどら焼きを買って帰ることにしました。
凄い行列!こんなに長い行列に並ぶのは初めてでした。前後の人たちは、どこから来たのか、雑談を楽しんでいます。お彼岸団子やおはぎ目当ての方が多いようです。
列に並んでいる間に、お店の外観を改めて見ることができました。すると、屋根に白いうさぎが飾られているのを発見!この行列に並んで良かったと思いました。
ソーシャルディスタンスをとりながらの長い行列でしたが、お店側の手際のよい作業であまり待つことなく無事どら焼きを購入することができました。4時頃までなら、どら焼きを購入できるようです。

ふわふわもちもちの生地に甘すぎないあんこが美味しい♪
おすすめの一品です。
http://www.ueno-usagiya.jp/
〒110-0005 東京都台東区上野1丁目10番10号
TEL: 03-3831-6195
定休日:水曜日
営業時間:午前9時~午後6時
9月21日は中秋の名月でしかも満月。

すすきを飾りました。
お月見をしているとリラックスして心が癒されます。
月のあかりが寝室まで灯してくれます。
夕方より空模様は下り坂。
雲の隙間からでもお月見ができますように・・・・。


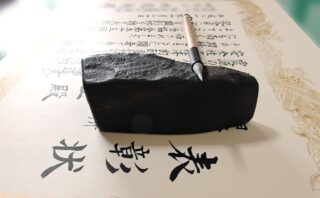






コメント