梅雨末期でゲリラ雷雨が続いていますが、お墓参りに行きました。
7月盆なので、13日が盆迎え火で16日が盆送り火です。
久々のお上りさんで、天気予報に持ち物チェックと前日から落ち着きません。
お盆の捉え方

7月盆と8月盆は、明治5年に政府が新暦を導入したことから都市部は7月盆に対応、すぐに切り替わらなかった地方などは昔からの慣習で全国的に多く見られる8月盆(旧暦盆)となったようです。お墓や仏壇を清めてお墓参りや仏壇にお供え物をして、先祖の霊をお迎えし供養して感謝するのが一般的です。
幼い頃から、仏壇に手を合わせることや、春や秋のお彼岸にはお墓参りをすることなど、よく理解していなかったまま習慣化して身につけていました。私自身があるのはご先祖様のおかげであり、彼らが見守ってくれていると感じていたからです。毎日、先祖の写真に囲まれて生活していると、彼らに見張られている!?という感覚があり、悪いことをすることができないなと感じることもありました。
今では、仏壇掃除は先祖の命日に実家に帰った時にする程度。お墓参りは春や秋のお彼岸とお盆の年3回です。
お墓参りというイベント

子供の頃、親と一緒にお墓参りに行くと、お寺の周辺には遊び場や飲食店などが数多くあり、お墓参りの後の行き先がとても楽しみでした。乗り物酔いしながらも、楽しい思い出を作るために頑張っていたものです。その当時は、動物園へ行ったり、洋服を買ったり、お子様ランチを食べたりしていました。しかし、時には思い描いていたような買い物ができず、帰りの電車で泣いてしまったことも今となっては、良い想い出です。
コロナ禍のお墓参りは家族を代表して一人で行くことが多くなりました。、お天気が良ければ、お寺の近くの公園を散策したりして非日常的な時間を楽しむことができます。
今年も綺麗な蓮の花が見事でした。
ちなみにピンクの蓮の花は、「信頼」の花言葉が付けられています。

お墓のあり方

時代の変化に伴い、お墓に関する問題や悩みが増えていることを耳にすることがあります。自分たち自身も、将来的には仏壇やお墓について考えなければならないという思いがあり、重く感じます。かつては、「墓は代々同じ家が継ぐもの」という考え方が一般的でしたが、少子高齢化や家族観の変化、社会の多様化により、お墓を継ぐ人がいない場合も増えています。今後、お墓のあり方がどのように変わっていくのか、私たちにとって大きな課題であることは間違いありません。
仏壇の掃除をするたびに、並んでいる遺影と目が合うと、どうしたら良いのか戸惑ってしまいます。自分が高齢になってお墓参りに行けなくなってしまう前に、墓じまいをすることになるのか、あるいは都合よくお寺で永代供養墓などに切り替えることができるのか、不安に思うことがあります。
墓じまい後の先祖の遺骨について、お寺に永代供養をお願いしたり、樹木葬や海洋散骨などの方法を選択することができます。代々の先祖をまとめて処理しなければならないとなると、決めるのが難しいことです。仏壇の処分にはお焚き上げ供養があり、墓じまいには閉眼供養がありますが、どちらにしても気が引けます。
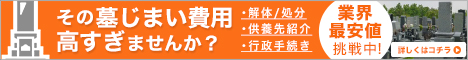
近年、家族葬が増加している中、通夜や告別式を行わずに直接火葬する直葬も選択肢の一つとして増えています。お葬式の準備は大変なため、合理的であるという意見もありますが、その一方で、故人を想う気持ちや弔意を表す場でもあるため、直葬に対しては様々な意見があります。
生前によく話し合いをしておけば、迷うこともありません。
人が一生を終えるまでは何かと大変。スッキリと整理して、次の世代が困らないようにしたいものです。


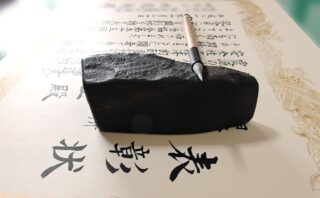






コメント